連載 新しい事業のつくり方
新しい事業のつくり方 第3回 システム1 必要なシステムとビジネスモデル
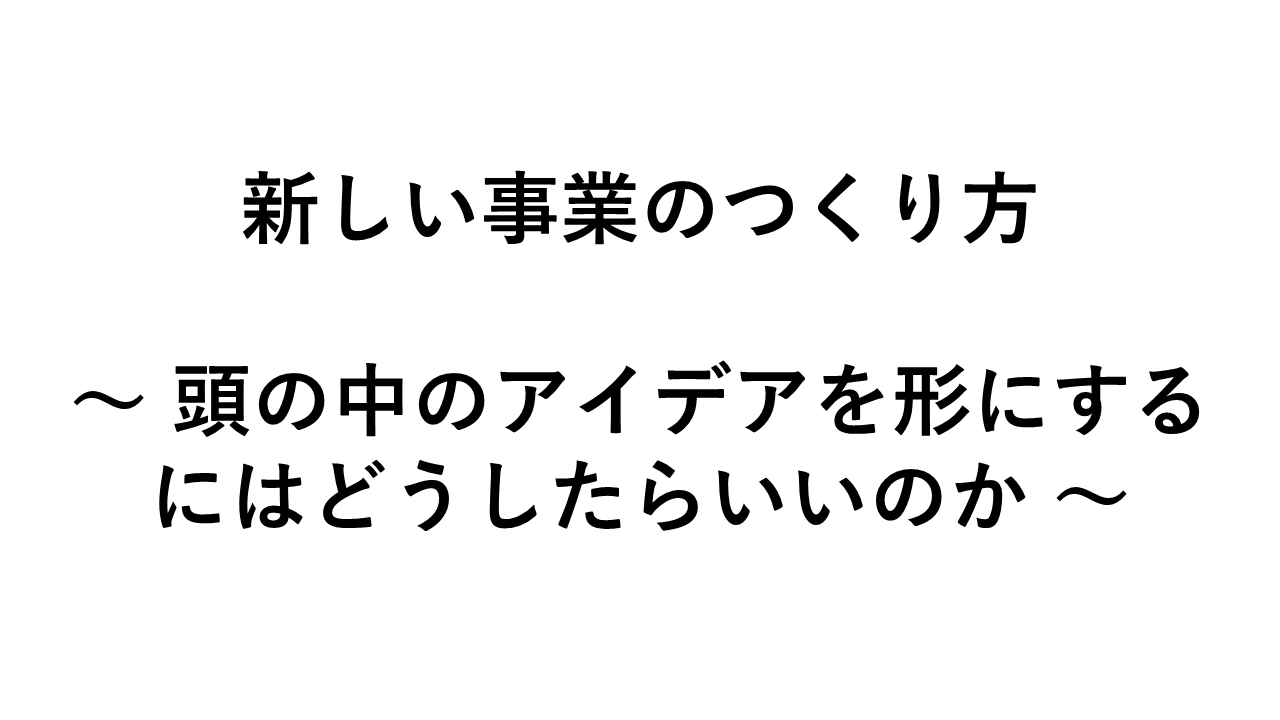
1. はじめに
今回から、事業を行うために必要な3つのインフラの1つ目として、システム(コンピューターシステム)について、お話したいと思います。
とはいえ、筆者は、IT技術者ではないので、IT技術に関する話ではなく、経営や法務の観点からの話が中心となります。
また、事業を行うに際してどのようなシステムが必要になるのかは、個別の事業の内容に影響を受ける部分も多いかと思います。しかし、特定の事業にフォーカスすると幅広い読者の興味に沿わないものになってしまうため、この連載では、ある程度、内容を一般化して、どのような事業においても当てはまるような話を中心に据えたいと思います。
なお、念のためですが、筆者からお話する内容は、あくまでも個人としての意見・見解であり、過去に所属した組織の見解やノウハウを記載するものではありません。また、内容としても、必ずしも網羅的で完全性を有するものではありません。
2. 必要なシステムの概要
まず、インターネットを介したB to C(対消費者向け)のビジネス、B to Small B(対小規模事業者向け)のビジネスを立ち上げる場合には、少なくとも、以下のシステムが必要になると考えられます。
【ウェブサービスを立ち上げるために必要となるシステム】
- ・ランディングページ(広告用ホームページ)
- ・申込受付システム(会員登録、サービスへの申込の受付等)
- ・サービス提供のためのシステム(会員サイト、ECサイトにおける商品ページ等)
- ・料金決済のためのシステム(カード情報入力と決済等)
ランディングページというのは、文字どおりサービスの「起点(はじまり)」となるようなページのことです。サービスの特徴やメリット等が記載され、ウェブ上での「チラシ」として広告の役割を果たすとともに、ここからサービス利用者をサービスの申し込み等の導線に誘導することになります。
また、メディアに広告出稿等を行う場合には、メディアからこのページに遷移させることになります。そして、ランディングページが検索結果に表示されやすくなるように、あらかじめサービス利用者のターゲットを設定して、ターゲットが検索しやすい用語をランディングページ上においてキーワードとして記載しておく必要があります。
申込受付システムというのは、文字通り、サービス利用者から申し込みを受け付けるためのシステムになります。「申し込み」というのは、契約締結のプロセスの一つであり、サービス利用者からの「申し込み」に対して、サービス提供者が、これを「承諾」した場合には、契約が成立することになります。
また、申し込みに際しては、サービス利用者から契約条件(利用規約)について同意を取得する必要があります。さらに、サービス提供者は、サービス提供のために、サービス利用者に関する一定の情報を取得する必要があります。
このように、申込受付システムは、サービス提供者が、サービス利用者から必要な情報の提供を受け、サービス利用者との間で所定の契約条件(利用規約)に基づいてサービス利用に関する契約を締結するために必要なシステムということになります。
さらに、ウェブサービスを立ち上げるためには、サービス提供のためのシステムが必要となります。例えば、ECサイトにおける商品ページ等が、これに当たります。また、フリマアプリなど、中古商品の売り手と買い手をマッチングさせるプラットフォームサービス(取引の「場」を提供するサービス)であれば、売り手側の情報を買い手側に表示するようなウェブページ等が、これに当たります。
サービス提供のためのシステムは、どのようなサービスを提供するのかによって、カスタマイズする部分が大きいシステムといえます。逆にいえば、競合他社との比較で、独自性や強みを発揮することができる分野ということもできます。
最後に、料金決済のためのシステムが必要となります。無償でサービスを提供して、サービス上に表示される広告によって収益化を行うのではなく、サービス提供者が、サービス利用者に対して、有償でサービスを提供する場合には、利用料金を円滑に決済する仕組みが必要となります。
3. 市場の参加者になるのか、運営者になるのか
上記では、インターネットを介したB to C(対消費者向け)のビジネス、B to Small B(対小規模事業者向け)のビジネスを立ち上げる場合に必要となるシステムの概要について見ていきましたが、amazon.com、楽天市場、ヤフオク、メルカリなど、現在、市場において有力な地位を占めるサービスにおいても、少なくとも、上記の機能を有するシステムが提供されていると考えられます。
また、最近では、ShopifyやBASEなど、自社でECサイトを開発しなくとも、ECサイトを構築するために必要な機能を提供してくれるサービスが存在しています。そのようなサービスにおいても、基本的には、上記の機能を有するシステムが提供されていると考えられます。
ECサイトによる商品の販売等、インターネットを介して物販を行うのであれば、自社でゼロからECサイトを構築して、その広告宣伝を行うよりも、上記のようなプラットフォームサービスに出店する方が、あるいはECサイト構築サービスを利用する方が、手数料は取られるものの、効率的であると考えられます。
特に、プラットフォームサービスやECサイト構築サービスでは、料金決済の機能が提供されているため(決済機能の提供がプラットフォームサービス等の「肝」といえます)、出店者(加盟店)は、より簡便に料金決済のための機能を使用ことができます。さらに、プラットフォームサービス等で提供される共通ポイント等の恩恵を受けることも可能となります。
他方で、自社が出店者としてユーザーに対して商品やサービスを提供するのではなく、プラットフォームの運営者として、ユーザー(買い手)と加盟店(売り手)の双方に対して、取引の「場」を提供するサービスを提供しようと思った場合には、少なくとも、上記の機能を有するシステムを開発しなければならない(又は他社の提供する機能を組み込まなければならない)ことになります。
自分が出店者(加盟店)としてユーザーに対して商品やサービスを販売するのか、あるいはプラットフォームの運営者として、ユーザーと加盟店に対して、取引の「場」を提供するサービスを提供するのかという問題は、ビジネスモデルの選択として興味深い論点といえます。
19世紀アメリカ西海岸でのゴールドラッシュに際して、一番儲かったのは、金を掘る人ではなく、金を掘る人に道具を売った(貸した)道具屋であったというジョークが残っています。また、同じく19世紀アメリカの石油産業において、ジョン・D・ロックフェラーは、石油の掘削ではなく石油の精製に目をつけてスタンダード・オイルを設立し巨万の富を築き上げました。
このように、多くの市場の参加者が目先の利益の獲得を競い合っている状況においては、一歩引いた形で、市場の運営者となることに注目した方が、日常のビジネスから生じるリスクは限定的であることに加え、成功した場合に得られる収益としては遥かに大きいものになると考えられます。
現代のITビジネスにおける醍醐味は、データの送受信という技術を使って、物理的な設備に対する巨額の投資から解放されて、誰でも、アイデアによって市場の運営者になれることにあります(もちろんサーバーやソフトウェアといった設備の調達は必要となります)。
ただし、プラットフォームサービスの立ち上げには、相応の資金と時間が必要となる点には注意が必要です。プラットフォームサービスを立ち上げること自体に、システム投資が必要となりますし、プラットフォームサービスを立ち上げたとしても、直ぐに収益化できるケースは少なく、まずはユーザーと出店者の双方にプラットフォームを使ってもらって参加者を集めなければなりません。
既にマーケットにおいて有力な地位を築いているプラットフォームであれば、出店者の方から率先して出店を申し込んで来ることもありますが、そうでなければ、目先の採算を度外視して、まずは魅力的な出品者を数多く集めなければなりません。
さらに、ユーザーに対して、プラットフォームの宣伝を行い、さらにポイント等の還元策を活用することで、初めて多くのユーザーをプラットフォームの利用者とすることが可能です。実際に、現在、市場において有力な地位を占めるプラットフォームサービスは、そのようなプロセスを経てきたと考えられます。
他方で、自社が他には無い希少な商品やサービス(スキル)を有していれば、プラットフォームの提供者にはならなくとも(出店者であっても)、短期間でマーケットにおいて有力な地位を築くことも可能であると考えられます。
結局のところ、自社のサービスに必要となるシステムの機能を検討していくことは、自社のビジネスモデルを検討していくことに直結しているといえます。