連載 新しい事業のつくり方
新しい事業のつくり方 第7回 オペレーション1 コンピュータやAIの進化とどう向き合えばいいのか
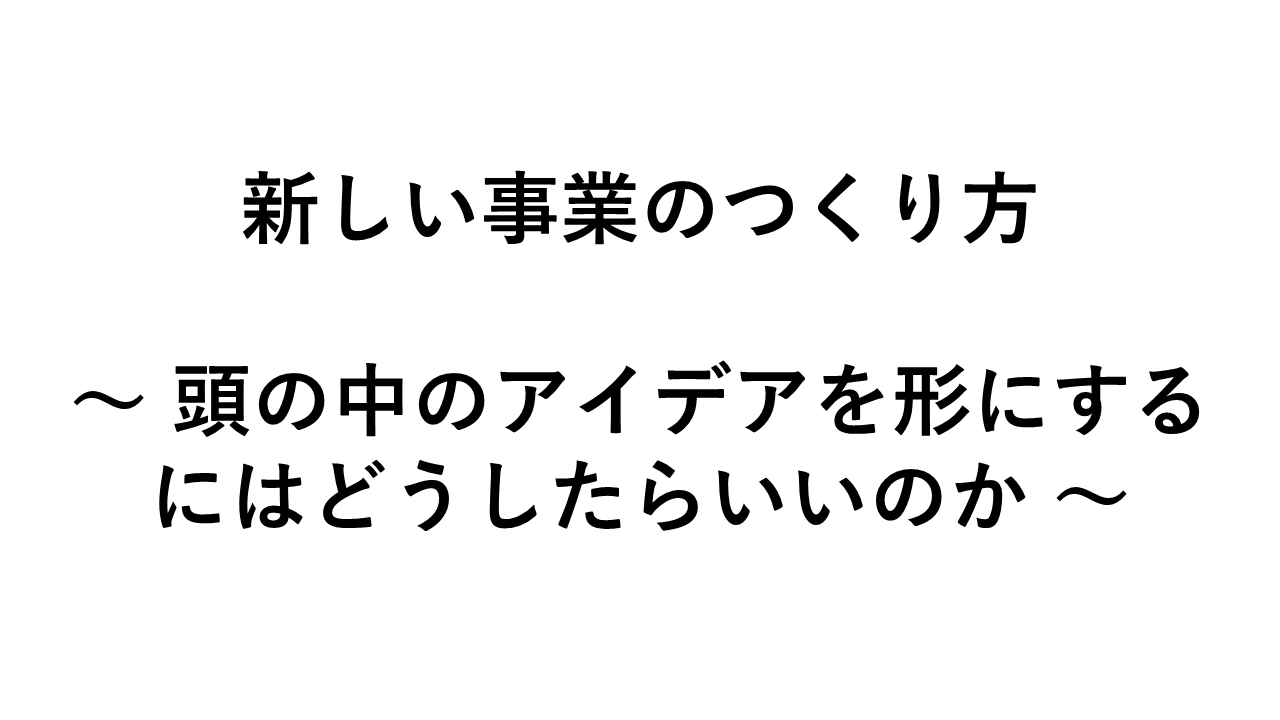
1. はじめに
今回から、強い事業を作るための3つのインフラのうち、2つ目のオペレーションについて説明をしていきたいと思います。今回は、総論的に、システムとオペレーションの関係、具体的には、何をシステムによって行い、何を人手によって行うべきであるのかという点について考えていきたいと思います。
AI(人工知能)やRPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)の進化に加えて、少子高齢化に伴う労働人口の減少等により、現在、何をシステムによって行い、何を人手によって行うべきであるのかという問題は、ビジネスにおける重要なテーマになりつつあると考えられます。
さらに、この問題は、筆者も含めてビジネスに関わる全ての人間(経営者も例外ではありません)が、どのように働き、どのような価値を残して、対価とやりがいを獲得していくのかという現代に生きるビジネスパーソンにとっての働き方の問題とも直結しています。
そこで、今回の記事では、事業をどう構築していくのかという観点に加えて、皆さんが、今後、どのように働いて、どのような価値を発揮していくべきであるのかという観点でも読んで頂けると、さらに面白いものになると思います。
なお、念のためですが、筆者からお話する内容は、あくまでも個人としての意見・見解であり、過去に所属した組織の見解やノウハウを記載するものではありません。また、内容としても、必ずしも網羅的で完全性を有するものではありません。
2. コンピュータの本質
まず、前提として、システムとオペレーションの関係は、「表裏一体のもの」と考えることができます。即ち、RPA(ロボティク・プロセス・オートメーション)も含めて、「サービス」に関する全ての業務プロセスがシステム化(自動化)されていれば、極論を言うと、人手は必要ありません。
他方で、AIが進化してはいるものの、現在のコンピューターシステムに関する技術では、少なくとも、最初から全ての業務プロセスをシステム化(自動化)することは難しいため、一連の業務プロセスについて、どこをシステム化して、どこを人手で行うのか、ということを考えていく必要があります。
ここで、少し話題を変えて、そもそも、システムを構成するコンピュータとは、一体何であるのか、即ち、コンピュータの本質とは何かという点を考えていきたいと思います。
筆者は、これを「計算機」であると考えています。刑法などの法律の規定では、少し古めかしい表現ですが、コンピュータのことを「電子計算機」と表現しています。
「計算機」であるということの意味は、もともとコンピュータは、軍事目的や科学目的の複雑な計算を行うために開発されたものということもありますが、その基本的な機能として、ユーザーによる「インプット」をもとに、プログラムが演算による「処理」を行い、結果を「アウトプット」として出力するものであることにあります。
このような、「インプット」、「処理」、「アウトプット」という機能は、非常に単純な例を挙げれば、ユーザーが文書作成ソフトを立ち上げてキーボードで「あ」という文字を打つと、パソコンが処理を行い、ディスプレイに「あ」という文字を表示するというものになります。もっと複雑なものでは、生成AIのツールに対して、資料とプロンプト(AIに対して指示や質問を行うための入力)を入力すると、生成AIのプログラムが処理を行い、結果を文字や画像という形でディスプレイに出力するというものになります。
もちろん、文書作成ソフトでのキーボードによる操作と生成AIツールでは、プログラムによる「処理」の複雑さは、各段に異なります。しかしながら、プログラムによる「処理」が複雑になることで、コンピュータが本来持っている基本的な性質が変わる訳ではありません。
以上のような「インプット」、プログラムによる「処理」、「アウトプット」というコンピュータの本質的な機能を考慮すると、コンピュータの持つ特徴として、以下の点を挙げることができるのではないかと考えられます。
【コンピュータの機能から導かれるその特徴】
- ①パターン化された事項の「処理」が得意であり、イレギュラーな事項・突発的な事項をミスなく「処理」するには、より複雑で高度なプログラムが必要となる。
- ②コンピュータによる「処理」は、プログラムによる演算であり、人間の「感情」のようなメカニズムは本来備わっていない。また、「アウトプット」の方法は、ディスプレイや音声を通じての内容の表示が基本的なものとなる。
- ③プログラムによる「処理」を行う前提として、まず、「インプット」を行う内容を決めなければならない。
3. システム化せずに人手で行うことが望ましい事項
上記では、コンピュータの本質的な機能とその特徴を見てきましたが、これらを踏まえると、コンピュータにとっての「強い事項」(得意な事項)と「弱い事項」(不得意な事項)が見えてくることになります。そして、コンピュータにとっての「弱い事項」こそが、システム化せずに人手で行うことが望ましい事項につながってくると考えられます。
【コンピュータの特徴から人手で行うことが望ましい事項】
- ①パターン化し難いイレギュラー・突発的な対応が必要な事項
- ②コミュニケーションを用いて人間の感情を取り扱わなければならない事項
- ③インプットすべき内容やその程度などインプットの前提条件が決まっていない事項
なお、上記の事項については、コンピュータが「弱い」(得意ではない)といって、必ずしも人が「強い」(得意である)という訳ではない点には注意が必要となります。イレギュラー・突発的な事項への対応が得意か否かは、個人差が大きく、またコミュニケーションが得意か否かも、個人差が大きい事項といえます。
このように考えると、筆者も含めて現代に生きるビジネスパーソンが、コンピュータに代替されない人材になるためには、イレギュラー・突発的な事項に対して柔軟な対応ができ、コミュニケーションに長けて他人の感情を上手くコントロールすることが可能で、既存の前提条件に囚われずにゼロベースで物事を考えていくことができなければならないことになります。もちろん、一人の人間が全てを行うことができる必要はないのですが、それでも、このような人材になるのは、なかなか大変なことかと思います。
以下、順を追って説明をしていきます。
(1) パターン化し難いイレギュラー・突発的な対応が必要な事項
この点については、システム化に際しての制約事項として、「コスト」と「システム要件の明確化」が深く関係してくることになります。
まず、「コスト」については、我が国では、米国等と比べて、システムエンジニアの多くが、事業会社ではなくITベンダー等に勤務しているといわれており(2025年7月20日付日本経済新聞電子版)、自社で大規模なシステム開発のためのリソース(システムエンジニア等)を常時保有している企業は、多くはありません。
このため、システム開発を行うためには、程度の差こそあれ、外部にシステム開発を委託して開発を実施してもらう必要があります。したがって、システム開発を行うための「コスト」が、システム化を行う際の重要な考慮要素となります。
特に、イレギュラー・突発的な事項に対してコンピュータによってミスのない対応を行おうとすると、より複雑なプログラムが必要となります。そして、複雑なプログラムを組み込んだシステムを開発する際には、バグやエラーが生じないように、より慎重なテストを実施することが必要となり、その分、開発のための「コスト」の増加に直結することになります。
次に、システム開発を行うためには、システムに必要な機能や仕様等のシステムの要件を定義する必要があり、この要件定義が不十分なままシステム開発を進めると、完成したシステムが役には立たないものになってしまいます。このため、「システム要件の明確化」が、システム化を行う際の重要な考慮要素となります。
最近では、システム開発の手法として、アジャイル開発なども浸透してきており、ウォーターフォールモデルのように「要件定義」のプロセスが独立して設けられていないケースも見受けられます。しかしながら、システム開発のプロセスが変わったとしても、システム開発において何らかのプロセスを通じて「システム要件の明確化」を行うことが重要である点には、変わりはないものと考えられます。
そして、「システム要件の明確化」とは、どのような事態が起きた場合に、どのように処理を行って、アウトプットとして何を求めるのか、という点を予め明確にしておくことを意味します。
しかし、イレギュラー・突発的な事項については、ある程度の確率や周期で生じる予測可能な事態から、いつ起きるのか何が起きるのか予測不能な事態まで、様々なケースが存在しています。前者(ある程度の確率や周期で生じる予測可能な事態)については、プログラムを複雑化することで、ある程度対処することは可能となりますが、自然災害も含めて、後者(いつ何が起きるのか予測不能な事態)については、通常は、システム要件を明確化することは困難であると考えられます。
以上のように、「コスト」と「システム要件の明確化」の観点から、イレギュラー・突発的な事項に対する対応については、コンピュータではなく人手で行う方が、効率的で柔軟な対応が可能になると考えられます。
(2) コミュニケーションを用いて人間の感情を取り扱わなければならない事項
コンピュータの特徴を踏まえて、人手によって行った方が望ましい事項の2つ目は、「感情」と「コミュニケーション」が関係する事項です。
最近は、企業のカスタマーサポートにおいても、AIを用いたチャットボットが導入されつつあり、ユーザーがトラブルを抱えて企業のホームページ等にアクセスすると、まずは、チャットボットへの入力を余儀なくされるというケースも増えてきています。
皆さんは、サービスの利用に関してトラブルを抱え、イライラした状態で、チャットボットに入力を行い、いかにも杓子定規な回答が返ってきて、さらにイライラを増幅させたという経験をお持ちではないでしょうか。
この点は、もちろん、カスタマーサポートにおけるチャットボットツールが発展途上のものであるという問題もありますが、もっと根源的な問題として、プログラムによる演算、即ち「論理」(ロジック)のみで動くコンピュータと「感情」という「論理」とは異なる性質を基に行動する人との根本的なメカニズムの違いが存在していると考えられます。
即ち、コンピュータは、あくまでも演算によって動くものであり、一見すると「感情」を示しているような動きをするものであっても、疑似的に「感情」を示しているような動きをさせているに過ぎません。
さらに、人の感情は、他の動物のものとは異なり、もっと複雑・多様であり、予測不能な動きをすることになります。そして、論理的に考えると正しい回答であったとしても、人は、必ずしも、それに納得をして、その通りに動いてくれるものでもありません。人は、必ずしも、合理的な判断をする訳ではなく、時として、非合理的な行動をとる事態さえ生じます。
以上のように、コンピュータが出した「論理的に正しい答え」に対して、人は「感情」のレベルで納得感や共感を持つことができる訳ではなく、逆に、「論理的に正しい答え」に対して反感を感じるケースすら生じることになります。
さらに、コンピュータにはない特徴として、人は、極めて多様なコミュニケーションの手段を持ち合わせており、時として、コミュニケーションの手段を用いて、相手の感情をコントロールすることが可能な点が挙げられます。
即ち、人は、アウトプットの内容を、言語、文字、絵によって相手に伝えるだけではなく、顔の表情、声色、身振り・手振り、相手に対する相槌、沈黙(沈黙も重要なコミュニケーションの手段の一つです)等、あらゆる手段を使って、自己の感情とともにアウトプットの内容を表現することができ、これによって、相手に対して、喜怒哀楽を含めて様々な感情(納得、共感、喜び、怒り、恐怖、悲しみ等)を抱かせることが可能といえます。
もちろん、自分の思わぬ発言が相手を怒らせてしまうこともあり、コミュニケーションによって相手の感情を100%コントロールすることは難しいのですが、熟練した営業マンのように、経験を積み重ねることで、相手の感情をコントロールする技術が上手くなっていくということは十分に考えられます。
以上をまとめると、人は、コンピュータとは異なり「論理」ではなく「感情」で動く生き物であり、さらにアウトプットの内容を表示する以外にも多様なコミュニケーション手段を持ち合わせているため、アウトプットの内容とともに、そのようなコミュニケーション手段を駆使して自己の感情を表現することで、相手の感情をコントロールすることが可能なケースが存在しています。
そのような特徴を踏まえると、コミュニケーションによって人の感情を取り扱うような場面、即ち、クレーム対応(ただし、初動のためにツールを使うことを否定するものではありません)、社外のステークホルダーとの何らかの交渉や折衝(大口の商談等も含む)、従業員のモチベーションの維持や各種の社内調整等の施策については、システム化するよりも人手で行うことが望ましいと考えられます。
(3) インプットすべき内容やその程度などインプットの前提条件が決まっていない事項
最後に、コンピュータの特徴を踏まえて、人手によって行った方が望ましい事項の3つ目として、インプットの前提条件が決まっていない事項について説明します。
これまでお話してきたとおり、コンピュータでは、ユーザーが「インプット」した内容をもとに、プログラムが演算による「処理」を行い、「アウトプット」を出力することになります。例えば、生成AIツールを使用する際にも、まずはユーザーが資料やプロンプトを入力することが必要となります。
少し唐突ですが、上記のプロセスは、ある問題が、適法であるのか違法であるのかを回答する法律相談の構造と似ている部分があります。即ち、法律相談では、問題となる行為や取り組み内容等をもとに、前提となる事実関係を確定し、その事実関係を法律の規定や判例等に当てはめることで、適法なのか違法なのかという答えを導き出すことになります。
ただし、法律相談においては、問題はそう簡単ではありません。そもそも、前提となる事実関係自体があやふやであり、また紛争が生じている場合には、紛争の相手方の認識している事実関係とは異なるケース(事実関係に争いがある)も数多く存在しています。
実際の法律相談においては、法人からの相談であれ、個人からの相談であれ、最初から、法律判断に必要な事実関係について網羅的に整理された形で説明を受けるケースは多くはなく、コミュニケーションを取りながら、こちらからも色々と質問をしていく中で、隠れていた事実を導き出して、事実を裏付ける証拠や確度を確認し、また事実と事実の間のつながりや因果関係を明らかにして、出来事の全体像を把握していくことになります。
以上は、法律相談におけるインプットの問題ですが、インプットすべき情報の重要性については、コンピュータを使用する場合、例えば、生成AIツールを使って何らかの問題を解決する場合にも当てはまるものと考えられます。
具体的には、ある契約を締結しようと考えているときに、生成AIツールに対して、契約書のドラフトと自社にとって最も有利な条項が記載されている「モデル契約書」をインプットして、契約書のドラフトを、自社にとって最も有利な形に修正してほしいというアウトプットの作成を指示することにします。このように単に自社にとって「有利な契約書を作る」という目的であれば、インプットすべき内容は明確であるといえます。
しかしながら、ビジネスの現場において考慮しなければならない事項は、もっと複雑多岐に渡っています。即ち、単に目の前の相手方と契約する契約書の内容を自社に少しでも有利にすればよいという訳ではなく、相手方との交渉力の違いから、そもそもどこまで有利にすることが可能なのかという問題があります。
さらに、目の前の相手方が自社にとっての「顧客」なのであれば、自社と顧客との契約だけで取引が完結するものではなく、自社にとっての「仕入先」等の商流全体を見て、取引に関するリスクがどうなっているのかを判断していく必要があります。
これに加えて、ビジネスにおいては、契約書に表れていない様々な考慮要素が存在しています。例えば、確かに目の前の契約書は、自社にとって不利な内容になっているが、この取引を通じて顧客に価値を提供できれば、次にもっと大きな取引につながる相当程度の可能性が存在する場合もあります。まさに「損して得取れ」というべき状況です。
以上のような諸事情を考慮して、「今回の取引において最善の契約書を作る」という目的であれば、まず、インプットすべき情報は何であり、それをどの程度考慮すべきであるのかを決定する必要が出てきます。
このようなインプットをすべき前提条件の決定は、コンピュータではなく、人が行うことが望ましい作業であると考えられます。なぜならば、インプットすべき内容として、何を重視すべきであるのかという点は、人(個人や組織体の構成員)が、その問題に関して何を重視しているのかという価値観と直結する問題であるといえます。
即ち、なるべくリスクを抑えて取引を行いたいのか、ある程度リスクを取ってでもリターンを追求したいのかは、個人や組織体の価値観に基づいて意思決定を行うべきであり、それをコンピュータに丸投げすべきではありません。
4. まとめ
今回は、やや抽象的な内容となってしまいましたが、昨今、AIの性能が非常に速いスピードで高まっていく中で、何をコンピュータに任せて、何を人手によって行うべきであるのかという点を考えてきました。
そのことは、コンピュータが進化していく中で、筆者を含めて、ビジネスに関わる全ての人材が、何を行えば価値を残していくことができ、仕事を通じて対価ややりがいを得ていくことができるのかという答えにも、直結していると考えられます。
筆者自身は、コンピュータは、あくまでも「ツール」であるというスタンスです。その「ツール」を使って、どのような価値を作り出すのかという点が重要であると思っています。