連載 新しい事業のつくり方
新しい事業のつくり方 第1回 顧客ターゲットとサービス内容
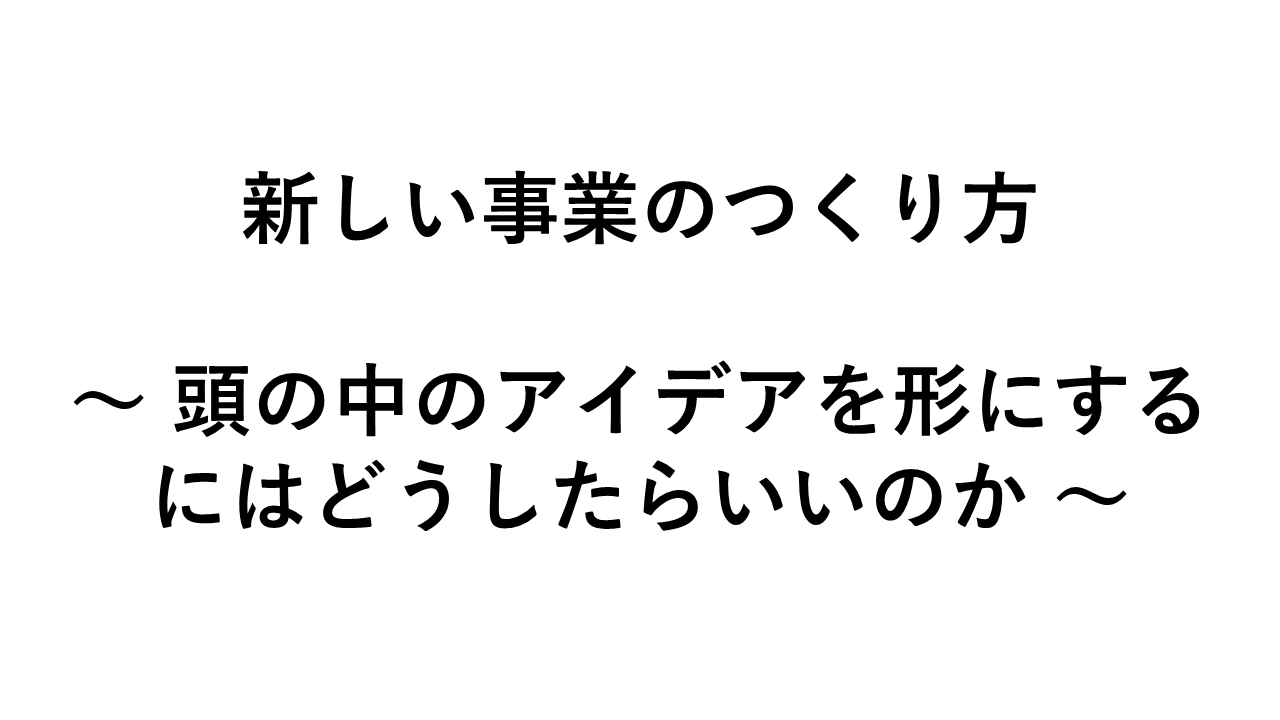
1. はじめに
これから何回かに分けて、起業や社内で新しい事業の立ち上げを考えている方に向けて、頭の中にあるビジネスのアイデアを形にしていくにはどうすればいいのか、というテーマでお話をしていきたいと思います。
筆者は、これまで、主に、弁護士や法務の立場でビジネスに関わってきたため、法務的な観点が中心にはなりますが、過去2年間、国税庁(東京国税局)に勤務して、大規模法人の税務調査等に関わってきた経験もあるので、会計や税務の観点も織り交ぜてお話をさせて頂きたいと思います。
また、過去には、ITベンダーにおいてプログラミングも含めてシステムエンジニアとしての研修を受け、短期間ですがITコンサルタントとして仕事をしていた時期もあるので、テクノロジー(情報通信技術)に関する話題も織り交ぜてお話できればと思っています。
さらに、筆者がこれまで関わってきたのは、ITビジネス、金融ビジネス(証券、銀行、クレジットカード、FX、保険等)等が中心になるため、メーカーや製造業のように「物」としての商品を作るビジネスに関することよりも、「サービス」を中心としたビジネスに関するアドバイスを得意としています。
そのため、これからお話することは、「サービス」を中心としたビジネスの話にはなりますが、メーカーや製造業のビジネスにも当てはまらない訳ではありません。なぜならば、例えば、トヨタ自動車が、単に自動車を製造・販売するだけでなく、自動車に関連する様々なサービスを提供することで、消費者に対して「体験」や「価値」を提供する企業に進化しているように、現代のビジネスにおいては、単に商品を製造して販売するだけでは、新興国の企業において企画及び製造される安価な商品に太刀打ちすることはできません。
そこで、製造業やメーカーであっても、これまでの「ものづくり」のノウハウやビジネスモデルを活かしながら、ITビジネスや金融ビジネス等の「サービス業」のノウハウや発想を取り入れて、ユーザーに対して、「体験」や「価値」を提供していくことが重要となります。
これからお話する内容は、そのような観点で見れば、メーカーや製造業等の「ものづくり」を行っている企業にもっても、役に立つ部分が多いのではないかと考えています。また、インターネットを通じた物販(小売業)のように、自ら製品を製造せず、仕入れた製品を販売するビジネスについても、当てはまる部分が多いのではないかと思っています。
なお、念のためですが、筆者からお話する内容は、あくまでも個人としての意見・見解であり、過去に所属した組織の見解やノウハウを記載するものではありません。また、内容としても、必ずしも網羅的で完全性を有するものではありません。
2. 顧客ターゲットの設定とサービス内容の構築
(1) 顧客ターゲットの設定
まず、「事業」を立ち上げるに際しては、誰を顧客のターゲットにして、どのようなサービスを提供するのかという点が問題となります。その中でも、顧客の対象は、大きく分けると、消費者を相手にするのか(B to C)、小規模事業者を相手にするのか(B to Small B)、大企業を相手にするのか(B to B)、という観点で分類することができます。
そして、誰を顧客のターゲットとするのかによって、サービスの内容だけでなく、必要なビジネスのインフラ(後で説明する、システム、オペレーション及び契約等)が変わってくることになります。
読者の方がどのような組織に所属して事業を立ち上げようとしているのかという点にもよりますが、大企業において新規のビジネスを立ち上げるのではなく、個人又は小規模な組織に属する方が、いきなり対大企業向け(B to B)のビジネスを立ち上げるのは、難しいケースが多いと考えられます。
例えば、M&Aの仲介などは、特別な資格は必要ではなく(ただし、2026年度から中小企業庁が資格を設けることも検討されているようです)、極論を言えば、電話とPCがあれば事業を立ち上げることは可能です。
しかし、特別なコネクションやバックグラウンドを有している場合を除き、いきなり上場企業等を対象として手数料の大きいディールに焦点を当てたM&Aアドバイザリーファームを立ち上げることは難しく、1件当たりの手数料の金額は大きくはなくとも、小規模企業等の事業承継等を対象としたM&Aの仲介ビジネスを立ち上げる方が無難な対応といえます。
こういうと、随分と小粒に小さくまとまったことを言うように聞こえるかもしれませんが、これは、そもそも「事業」というものの「本質的な要素」をどうように考えるのかという問題と関係しています。
(2) 「事業」の本質的な要素とは
皆さんは、「事業」を立ち上げたい考えたとき、「事業」というものの本質的な要素を何だとお考えでしょうか?即ち、もっと簡単にいうと、「事業」にとって何が一番重要であるとお考えでしょうか?
「儲かること」、即ち、営利性があることでしょうか。もちろんそれも必要ですが、少なくとも、法律(法務)的な視点から見た場合には、もっと本質的な要素が存在しています。それは、「反復継続性」(繰り返し行うこと)を有することです。
これは、法律の分野では、「業務上横領」(刑法第253条)での「業務」や「貸金業」(貸金業法第2条第1項)での「業として行う」という場面で現れてくることになります。
即ち、「業務上横領」は、「単純横領」よりも刑罰が重く定められており、これは、ある行為を反復継続して行う者にはより高度な注意義務が必要とされるべきと考えられていることによります。
また、金銭の貸付け等に関して、特定少数の者に対してであっても、繰り返しこれを行う者に対しては、「貸金業者」としての登録を必要にして所管官庁の監督の下に置き、一定の義務を課するべきであると考えられています。
これに加えて、税務の分野でも、所得税法上、損失の繰り越しや他の所得との損益通算等が認められる「事業所得」に該当するための要件として、判例(最高裁昭和56年4月24日判決)は、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」ものと判示しています。経済的な観点を加味したとしても、反復継続性のない利益には、事業所得としての性質は認められないといえます。
このように、問題となる法律や分野によって必要とされる要件は微妙に異なりますが、法律や税務の分野では、「事業」や「業務」といった場合には、「反復継続性」(繰り返し行うこと)が中心的な要素と考えられている点は、疑う余地がありません。
そして、この「反復継続性」(繰り返し行うこと)とは、言い方を変えると、「再現性」(同じやり方を再現できる)を有することと考えることができます。即ち、「事業」を立ち上げることを考えた場合には、「一回だけ上手くいく」ことや「たまたま上手くいく」ことは、その本質的な要素とは相容れないことになります。
例えば、数回の不動産、株式、暗号資産の取引で巨額の利益を上げたとしても、それは単に「儲かっただけ」であって、「事業」を立ち上げたことにはなりません。
勘違いしてほしくないのは、筆者は何も不動産、株式、暗号資産の取引を否定している訳ではありません。それを再現性のあるやり方で仕組化して、反復継続して行うことができれば、「事業」に該当すると思っています。
ここで重要なことは、「営利性」(儲かること)は、再現性のある仕組みを作りあげるために必要な要素であって(生活の糧を得るための手段として、儲からないことを反復継続し続けることは現実的に難しい)、「事業」にとって最も重要で本質的な要素とはいえないということです。
「事業」にとって最も重要で本質的な要素は、「再現性のある仕組みを作ること」にあることを意識する必要があります。
もちろん、ビジネスや私達の生活は、偶然や予期できない出来事によって左右されることが多く、思いもよらないことが起こります。
そうであるからこそ、「事業」を作っていく上で、上手くいった時には、何故それが上手くいったのかを考え、再現をして仕組化(パターン化)するという作業が不可欠といえます。また上手くいかなかった時には、何故それが上手くいかなかったのかを考えて原因を取り除き、次回は上手くいくパターンを仕組化していくという作業も不可欠といえます。
話を戻すと、何故、事業を立ち上げる際に、まずは大企業を顧客とした「B to B」のビジネスではなく、「B to C」(対消費者)や「B to Small B」(対小規模事業者)のビジネスを立ち上げるべきなのかというと、大企業を相手としたビジネスは、ケースバイケースの対応(専門化、細分化した要求への対応)を求められることが多く、再現性を確保するのが難しいことによります。例えば、M&Aアドバイザリーファームを立ち上げ、強力なコネクションや特定の業界に特化した知見を持っていたために、大企業を相手とした大きなディールを扱うことができたとします。
しかし、自社で相応のリソース(資金、人員、ノウハウ、信用など)を有していなければ、そのようなディールを再現し、ましてや繰り返し受注して仕組化することは難しいと考えられます。
そうであるからこそ、最初は、ターゲットの絶対数が多く、サービスに専門化・細分化の要素が低い、対消費者や対小規模事業者向けのビジネスを立ち上げるべきであるといえます。なお、補足すると、ここでいうターゲットの絶対数とは、まだ世の中にニーズが顕在化していない潜在的な顧客も含めての数で考えるべきであるといえます。
ただし、逆にいえば、大企業を相手としたビジネスであっても、「反復継続性」(再現性のある仕組みを作ること)ができるのであれば、むしろ差別化による強みを発揮できるので、これをターゲットとすることを否定するものではありません。
(3) 他社との差別化とサービス内容
さらに、「反復継続性」をポイントにして、どのような「事業」を作り上げるべきであるのかという点を考えていった場合、顧客となるターゲットの絶対数が多く、サービス内容の再現性が高いビジネスであればあるほど、競合他社による模倣(真似をすること)も容易となり参入障壁も低くなることから、競合他社による参入により、マーケット全体で見た場合には、自社による事業遂行の継続性(反復継続性)が逆に低下する危険性すら生じかねないことになります。
したがって、単なる自社による再現性だけではなく、自社の強みや競合他社による模倣の困難性といった観点も、「反復継続性」を考える上では、重要な要素といえます。
他方で、「事業」立ち上げの初期段階で、いきなり自社の強みや競合他社による模倣が困難なサービスを提供することは難しいともが考えられます。さらに、競合他社による模倣が困難なサービスを作ることは、「反復継続性」の構築(再現性の確保)とは、そもそも矛盾する問題といえ、競合他社による模倣が困難なサービスを作ることで、自社による再現性の確保も難しくなるというジレンマに陥る危険性すら存在しています。
そのため、具体的なアクションプランとして、最初は、単純なパターン化によって限られたバリエーションのサービスを提供しつつ、徐々にサービスのバリエーション(パターン化の数)を増やし、それらを組み合わせることで(例えば、IT業界と税務に強いM&Aアドバイザリーファーム)、自社の強みや競合他社による模倣の困難性を確保するという方法を取ることが考えられます。
3. まとめ
以上をまとめると、「事業」を立ち上げるに際して、誰を顧客のターゲットにして、どのようなサービスを提供するのかという問題については、自社による「反復継続性」という観点から以下のポイントで考えていく必要があります。
【顧客ターゲットとサービス内容に関するポイント】
- ①顧客となるターゲットの絶対数が相応に多いこと(潜在的なものも含む)
- ②サービスの仕組化(パターン化)が可能であること
- ③自社の強みを発揮し、競合他社による模倣が困難であること(パターン化の数を増やし、組み合わせができること)